テーマ2-2:衛星光通信の導入・活用拡大に向けた端末間相互接続技術等の開発
テーマID: theme2_2
カテゴリ: 衛星等(第二期)
作成日: 2025-10-22
テーマ2-2:衛星光通信の導入・活用拡大に向けた端末間相互接続技術等の開発
概要
利用可能な周波数資源の逼迫が深刻化する中、国際周波数調整が不要な光通信技術は、今後の衛星通信において極めて重要な役割を果たすことが期待されています。しかし、現状では衛星光通信端末の相互接続に関する広く共有された標準が存在せず、製造事業者や規格を横断した十分な相互接続が確保されていません。
この課題により、複数の衛星との光通信を行う際には同一端末を搭載する必要が生じ、コスト増加や設計上の制約といった問題が発生しています。また、衛星光通信は高精度の捕捉追尾技術が必要であり、衛星姿勢の乱れや微振動・温度変動への対応が求められます。
さらに、軌道設計段階において、既存の海外ソフトウェアが衛星光通信に十分に対応できておらず、検討作業に不確実性と負担を伴うという課題も指摘されています。
本テーマでは、これらの課題を解決するため、衛星光通信端末の相互接続確保に関する技術開発と、軌道投入前の検討を容易にするツール・ソフトウェアの開発を支援します。
技術開発の内容
本テーマでは、以下の技術開発を対象とします:
1. 衛星光通信端末の相互接続技術
異なる製造事業者・規格の光通信端末間での相互接続を実現する技術開発を支援します:
通信プロトコル標準化
- 共通通信規格の策定:製造事業者や規格を横断した共通プロトコルの開発
- インターフェース仕様の統一:光通信端末の物理層・データリンク層の標準化
- 相互運用性試験方法の確立:異なる端末間での通信試験手順の策定
- 国際標準化活動への貢献:CCSDS(宇宙データシステム諮問委員会)等での標準化推進
光学系の相互接続性向上
- 波長標準の統一:使用する光波長の標準化による相互接続性確保
- ビーム拡散角の最適化:異なる端末間でも捕捉可能なビーム特性の設計
- 偏光制御技術:偏光状態の統一による受信性能の安定化
- 光強度調整機能:通信距離に応じた送信光強度の自動調整
捕捉・追尾・通信(ATP)技術の標準化
- 捕捉シーケンスの共通化:初期捕捉から通信確立までの手順統一
- 追尾アルゴリズムの標準化:高精度追尾を実現するアルゴリズムの共有
- ハンドオーバー技術:複数衛星間の通信切り替え手順の標準化
- 異常検知・復旧手順:通信断発生時の自動復旧プロセスの統一
2. 軌道設計支援ツール・ソフトウェアの開発
衛星光通信を考慮した軌道設計・検討を容易にするツール開発を支援します:
軌道設計ツール
- 可視性解析機能:衛星間・衛星-地上間の可視条件自動計算
- 通信機会最適化:コンステレーション配置の最適化による通信機会最大化
- リンクバジェット計算:距離・姿勢を考慮した通信品質の自動評価
- ドップラーシフト補正:相対速度による周波数シフトの自動計算
姿勢制御シミュレーション
- 捕捉追尾精度評価:姿勢制御精度が通信品質に与える影響の解析
- 微振動影響解析:リアクションホイール等の微振動による通信断リスク評価
- 温度変動補償:軌道上温度変化による光学系変形の影響評価
- 姿勢マヌーバー時の通信維持:姿勢変更時の通信継続性評価
統合シミュレーション環境
- エンドツーエンドシミュレーション:地上局から複数衛星を経由したデータ伝送の全体評価
- ミッションシナリオ検証:実運用を想定した通信シーケンスの事前検証
- 性能評価指標の可視化:通信成功率、データレート、遅延等の自動グラフ化
- 既存ツールとの連携:STK(Satellite Tool Kit)等の軌道解析ツールとの統合
期待される効果
本テーマによる技術開発により、以下の効果が期待されます:
衛星光通信の普及促進
- 端末間相互接続性の向上によるコスト削減
- 複数製造事業者の端末を柔軟に選択可能
- 衛星コンステレーション構築の加速
- 国際競争力のある国産光通信端末の育成
軌道設計・開発の効率化
- 軌道設計段階での不確実性の低減
- 開発期間の短縮とコスト削減
- 光通信を考慮した最適なコンステレーション設計
- 国産ツールによる技術の自律性確保
宇宙産業全体への波及効果
- 衛星通信の大容量化・高速化の実現
- 周波数資源の有効活用
- 新たな宇宙ビジネスの創出
- 国際標準化活動における我が国のプレゼンス向上
公募情報
公募スケジュール
| 項目 | 日程 |
|---|---|
| 公募開始 | 2025年7月11日 |
| 応募締切 | 2025年9月4日(正午) |
| 一次審査(書面) | 2025年9月~10月上旬 |
| 二次審査(ヒアリング) | 2025年10月中旬~11月中旬 |
| 結果通知 | 2025年11月下旬~12月頃 |
応募要件
必須要件
- e-Radの機関・研究者登録が完了していること
- 国内に研究開発拠点を有する日本の法律に基づく法人格を持つこと
- 研究代表者・研究分担者は日本の居住者であること
- 相互接続技術またはツール開発の専門知識と実績を有すること
実施体制要件
- 衛星光通信技術の知見・技術開発実績を有すること
- 標準化活動への参画実績または参画意欲
- 複数の衛星事業者との連携体制(相互接続技術の場合)
- ソフトウェア開発の実績と品質保証体制(ツール開発の場合)
審査基準
主な審査・評価の観点:
- 技術開発の実現可能性
– 相互接続技術またはツールの技術成熟度(TRL)と開発計画の妥当性
– 標準化に向けた取り組みの具体性(相互接続技術の場合)
– ツールの機能仕様と開発方法の適切性(ツール開発の場合)
- 産業への波及効果
– 衛星光通信の普及促進への貢献度
– 国内衛星事業者の競争力強化への寄与
– 国際標準化への貢献可能性
- 実施体制・マネジメント
– 光通信技術またはソフトウェア開発の専門性
– 研究代表者のリーダーシップ・マネジメント能力
– 衛星事業者・製造事業者との連携体制
- 持続性・発展性
– 技術開発成果の継続的な維持・発展計画
– 国際標準化活動への継続的な参画計画
– 開発成果の商用化・普及戦略
技術的課題と留意点
本テーマの技術開発においては、以下の点に留意が必要です:
相互接続技術の課題
- 既存システムとの互換性:既に運用中の光通信端末との後方互換性確保
- 性能劣化の回避:相互接続性確保により通信性能が低下しない設計
- セキュリティ:標準化による通信の傍受リスクへの対策
- 知的財産権:標準化に伴う特許権の取り扱い
ツール開発の課題
- 精度検証:実際の軌道上データとの比較によるツール精度の検証
- ユーザビリティ:衛星設計者が容易に使用できるインターフェース設計
- 拡張性:将来の光通信技術進化に対応可能なアーキテクチャ
- 保守・サポート:長期的なツール維持管理体制の確保
標準化活動の課題
- 国際協調:海外の標準化活動との整合性確保
- 産業界の合意形成:国内外の製造事業者との調整
- 知財戦略:標準必須特許(SEP)の取得と管理
- 実証試験:標準化案の妥当性検証のための実証計画
関連情報
国際的な標準化動向
CCSDS(宇宙データシステム諮問委員会)
- Optical Communications Working Groupでの活動
- SCCS(Spacecraft Communications and Control Subsystem)の標準化
- 光通信プロトコルの標準化検討
IOAG(機関間宇宙通信諮問グループ)
- 各国宇宙機関による光通信の相互運用性検討
- 国際的な光通信ネットワーク構築に向けた協議
国内の関連技術開発
JAXA等による技術開発実績
- 光データ中継技術(LUCAS)の開発
- 光衛星間通信実験(OICETS「きらり」)
- 次世代光通信技術の研究開発
関連資料
まとめ
テーマ2-2「衛星光通信の導入・活用拡大に向けた端末間相互接続技術等の開発」は、衛星光通信の普及促進に不可欠な相互接続技術の確立と、軌道設計・検討を効率化するツール開発を支援する重要なテーマです。
端末間相互接続の標準化により、複数製造事業者の端末を柔軟に選択可能となり、コスト削減と開発効率化が実現されます。また、国産の軌道設計ツール整備により、光通信を考慮した最適な衛星設計が容易になり、我が国の宇宙産業の競争力強化に貢献します。
応募締切は2025年9月4日(正午)です。衛星光通信技術やソフトウェア開発の専門知識を有し、標準化活動や産業界との連携に意欲的な企業・研究機関の皆様は、ぜひご応募をご検討ください。

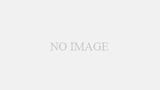
コメント