テーマ2-11:空間自在利用の実現に向けた技術
テーマID: theme2_11
カテゴリ: 衛星等(第二期)
作成日: 2025-10-22
テーマ2-11:空間自在利用の実現に向けた技術
概要
宇宙空間の自在な利用を実現するためには、大型軌道構造物の輸送制約、増大するスペースデブリの脅威(特に小型デブリ)、そしてカタログ化・除去技術の不足という3つの主要な障害が存在します。
本テーマでは、軌道上製造・組立技術、軌道上物体除去技術、宇宙状況把握技術の3つの開発領域を推進し、従来の制約を打破して宇宙空間の持続可能な利用を実現します。
技術開発の内容
本テーマでは、以下の技術開発を対象とします:
1. 軌道上製造・組立技術(A)
宇宙空間での直接製造・組立により、従来の輸送制約を克服する技術を開発します:
軌道上3Dプリンティング
- 金属3D印刷:宇宙空間での金属部品製造
- 複合材料造形:軽量高強度部品の直接製造
- 大型構造物製造:地上では製造困難な大型部品の軌道上製造
- 無重力環境活用:地上では不可能な形状・構造の実現
軌道上溶接・接合
- 自動溶接技術:ロボットによる自動溶接
- 各種接合法:溶接、接着、機械的接合の最適活用
- 品質検査:溶接品質のリアルタイム監視
- 真空環境対応:宇宙環境に特化した接合技術
大型構造物組立
- モジュール組立:複数モジュールの軌道上組立
- 展開構造技術:コンパクトな打上げと大型展開の両立
- 精密位置決め:高精度な部品位置合わせ
- 自律組立ロボット:無人での組立作業実現
材料技術
- 宇宙環境耐性材料:放射線・熱サイクルに強い材料
- 軽量材料:打上げコスト削減のための軽量化
- リサイクル材料:軌道上での材料再利用
- 現地資源活用(ISRU):月資源等の活用準備
2. 軌道上物体除去技術(B)
従来の大型デブリ除去を超え、小型デブリの除去システムを開発します:
小型デブリ捕獲技術
- レーザー照射:小型デブリの軌道変更
- ネット捕獲:網による複数デブリの一括捕獲
- ロボットアーム:精密な捕獲・回収
- 磁気捕獲:磁性体デブリの捕獲
デブリ除去手法
- 軌道降下誘導:大気圏再突入による除去
- 高軌道への移動:墓場軌道への移動
- 破砕・溶融:レーザーによる微小化
- 回収・再利用:材料としての再利用
自律除去システム
- デブリ自動検出:AIによるデブリ認識
- 接近制御:安全な接近軌道生成
- 捕獲判断:自律的な捕獲タイミング判断
- 複数デブリ対応:効率的な除去順序決定
安全技術
- 衝突回避:運用衛星との衝突防止
- 破片飛散防止:除去作業時の新たなデブリ発生防止
- 軌道予測:正確な軌道予測と管理
- 緊急停止機能:異常時の即座の作業中止
3. 宇宙状況把握技術(C)
従来把握困難だったデブリ情報を捉える観測・追尾技術を開発します:
地上観測技術
- レーダー観測網:cm級小型デブリの検出
- 光学望遠鏡網:広域監視システム
- レーザー測距:高精度軌道決定
- 観測網統合:複数観測所データの統合
宇宙ベース観測
- 軌道上センサー:近距離からの高精度観測
- 赤外線観測:熱放射による検出
- マルチスペクトル観測:物体識別精度向上
- コンステレーション観測:複数衛星による広域監視
データ処理・カタログ化
- AI自動分類:機械学習による物体分類
- 軌道予測:高精度な軌道予測
- カタログデータベース:デブリ情報の統合管理
- 衝突リスク評価:衝突確率の自動計算
情報提供サービス
- リアルタイム警報:衝突リスクの即時通知
- 軌道情報提供:衛星事業者への情報提供
- API提供:外部システムとの連携
- 可視化ツール:デブリ分布の視覚的表示
期待される効果
本テーマによる技術開発により、以下の効果が期待されます:
宇宙利用の拡大
- 大型宇宙構造物の実現(大型アンテナ、太陽光発電衛星等)
- 輸送制約の解消
- 宇宙インフラの構築
- 新規宇宙ビジネスの創出
宇宙環境の持続可能性確保
- デブリ増加の抑制
- 安全な宇宙利用環境の維持
- 衛星衝突リスクの低減
- 将来世代のための宇宙環境保全
国際的プレゼンスの向上
- 宇宙持続可能性への貢献
- 技術的リーダーシップの発揮
- 国際標準化への貢献
- 宇宙外交での優位性確保
公募情報
公募スケジュール
| 項目 | 日程 |
|---|---|
| 公募開始 | 2025年6月27日 |
| 公募締切 | 2025年8月28日(正午) |
| 一次審査(書面) | 2025年9月~10月 |
| 二次審査(ヒアリング) | 2025年10月 |
| 結果通知 | 2025年11月~12月 |
応募要件
必須要件
- e-Radの機関・研究者登録が完了していること
- 国内に研究開発拠点を有する日本の法律に基づく法人格を持つこと
- 研究代表者・研究分担者は日本の居住者であること
- A(製造・組立)、B(除去)、C(観測)のいずれかの専門性を有すること
実施体制要件
- 宇宙機開発、製造技術、またはセンサー技術の実績を有すること
- 実証試験を実施可能な体制(A・B)または観測網構築能力(C)
- 商用サービス化に向けた事業計画
- 宇宙持続可能性への貢献意識
審査基準
主な審査・評価の観点:
- 技術開発の実現可能性
– 開発技術の技術成熟度と開発計画の妥当性
– 基本的障壁克服への貢献
– 実証計画の具体性
- 宇宙持続可能性への貢献
– デブリ問題解決への効果
– 安全な宇宙利用環境構築への貢献
– 国際的な宇宙持続可能性活動への寄与
- 事業性・市場性
– 商用サービスとしての市場性
– ビジネスモデルの妥当性
– 収益見通しと投資回収計画
- 実施体制・マネジメント
– 関連技術の専門性と実績
– 研究代表者のリーダーシップ・マネジメント能力
– 関連事業者との連携体制
関連情報
国内外の動向
海外のデブリ除去プロジェクト
- RemoveDEBRIS(英国):ネット捕獲・銛捕獲実証
- ClearSpace-1(ESA):大型デブリ除去
- ELSA-d(Astroscale):磁気ドッキング実証
軌道上製造
- Made In Space(米国):ISS上での3Dプリンティング
- Archinaut(米国):軌道上組立実証
関連資料
まとめ
テーマ2-11「空間自在利用の実現に向けた技術」は、軌道上製造・組立、デブリ除去、宇宙状況把握の統合的な技術開発により、宇宙空間の持続可能な利用を実現する重要なテーマです。
大型宇宙構造物の実現、小型デブリの除去、詳細な宇宙状況把握により、宇宙利用の拡大と宇宙環境の保全が期待されます。
応募締切は2025年8月28日(正午)です。宇宙機開発・製造技術・センサー技術の専門知識を有し、宇宙の持続可能な利用に意欲的な企業・研究機関の皆様は、ぜひご応募をご検討ください。

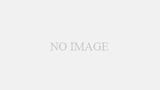
コメント